トップ > 暮らし・届出 > 防災・防犯・交通安全 > 備える > 地震に備えて
地震に備えて
更新日:2024年01月10日
09時19分
家族で防災ミーティング
地震はいつ何時発生するかわかりません。普段からお互いの連絡方法や避難場所について、よく話し合っておきましょう。
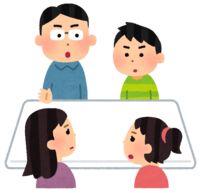
避難行動要支援者の保護
- 災害時には、誰が避難行動要支援者(高齢者、障害者、乳幼児)の安否確認、保護を行うかなどを決めておきましょう。
災害時の連絡方法及び避難場所の確認
- 避難所までのコース(避難経路)において、高いブロック塀や狭い路地がある場所を通行しないように、休日などを利用してご家族みんなで確認しておきましょう。
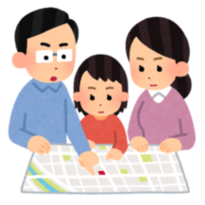
-
学校、職場の連絡先をまとめ、よく分かる所に貼っておきましょう。
家庭の安全対策チェック
家具の転倒防止
震災での人的災害の多くは家具が転到し、押しつぶされたり、出口がふさがれ火災から逃げ遅れたりしたことによるものです。
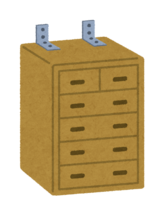
- 固定金具で固定する、または家具の下(手前)に板などを差し込んで、壁にもたせかける様にして固定します。
-
家具は人の出入りが少ない部屋にまとめておき、特に寝室や出入り口付近には大きな家具を置かないようにしましょう。
家の周りの安全対策
- プロパンガスの周りは鎖で固定する。
-
ブロック塀や石垣は補強しておく。
-
落ちそうな屋根瓦や不安定なアンテナは補修しておく。
-
道路に面したベランダに、落ちやすい物を置かない。
非常用持ち出し袋を準備しよう
このリストは、阪神淡路大震災を教訓として、人と防災未来センターが作成しました。
各家庭でいざという時に備える「非常持ち出し品」のチェックリストをまとめられています。
リストを参考に、あなたのご家庭で必要なセットの検討・用意をぜひ進めてみてください。

非常持ち出し品チェックリスト (844キロバイト)
(844キロバイト)
地震発生直後から3日間の対応
地震発生直後から3日間の対応について
| 震災後の時間経過 |
各対応内容 |
| 地震発生!! |
- まず身を守ることに徹します。机やテーブルの下などに身を隠し、寝ている時は布団や枕で頭を守ります。
- 小さな揺れでも火を消す習慣をつけておきます。但し、自動的にガスの供給を遮断するガスマイコンメーターが設置されている家庭においては、無理をして火を消す必要はありません。
|
| 1~2分後 |
- 避難口を確保します。ドア、窓を開けて脱出口を確保します。集合住宅はドアが開かなくなることがありますが、窓は比較的開きやすくなっています。
- 火元の確認と初期消火をします。
- 屋内でも靴を履きます。ガラスや破損物などから足を守り、すぐに避難できるようにしておきます。
- 家族の安全を確認します。家屋の倒壊、山崩れ(急傾斜地崩壊)などの危険があれば、直ちに避難します。屋外に出る時は、割れたガラスや瓦、看板等が落ちてこないか注意します。
|
| 3~5分後 |
- 非常用持ち出し品を手元に用意します。
- 隣近所の出火を確認します。
|
| 5~10分後 |
- 情報を収集します。テレビやラジオなどから正しい情報を集め、デマの情報に惑わされないようにしましょう。
- 地域(特に隣近所)の避難行動要支援者(高齢者、障害者、乳幼児)の安否を確認します。
|
| 10分後~数時間後 |
- 余震による家屋の倒壊や火災の延焼などの危険がある場合は避難します。
- 子供を学校などに迎えに行きます。
- 出火を防止します。ガスの元栓を閉めます。自宅を離れるときは、電気のブレーカーも落します。
- 自宅を離れるときは、行先をメモに書いて玄関などの目立つ所に貼り付けます。
|
| 数時間後~3日 |
- 非常備蓄品を取り出します。自足の生活が原則ですが、地域での助け合いも大切です。
- 自主防災組織や隣近所と協力して救出救護、消火活動等を行います。防災関係機関(警察、消防等)への通報も行います。
- 避難するときは集団で行動します。避難は徒歩とし、ブロック塀、切れた電線、ガラス窓には近づかないようにします。
- 行政、消防、警察等の広報に注意します。
|
▲このページの先頭へ
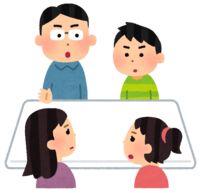
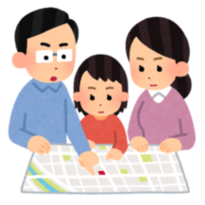
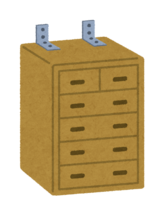

 (844キロバイト)
(844キロバイト)